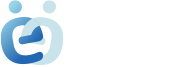新着情報news
2025.10.23
家族信託
認知症対策としての家族信託
判断能力が低下する前に、“財産管理の安心”を残す
「まだ元気だし大丈夫」
そう思える今こそ、できる対策があります。
認知症で手続きが止まる前に、家族がスムーズに動ける仕組みを一緒に整えましょう。
認知症になると何が困るの?
- 本人の判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の売却・賃貸、契約更新などが原則できなくなります。
- 成年後見制度を利用すれば一定の対応は可能ですが、原則“現状維持”が基本で、柔軟な資産活用(売却・再投資・承継設計など)は難しくなることがあります。
- 結果として、介護費用の確保や空き家化の防止が遅れ、家族の負担が大きくなりがちです。
家族信託でできること・できないこと
できること:
- 不動産の売却・賃貸・修繕、家賃収入の管理、生活費や介護費への充当など、契約で定めた範囲の柔軟な財産管理。
- 将来の承継先(受益者)や使途ルールを、家族の事情に合わせて細かく設計。
できないこと:
- 医療や介護の“身上監護”そのものは対象外(任意後見やご家族のサポートと併用)。
家族信託と任意後見の違い(要点)
| 項目 | 家族信託 | 任意後見 |
| 発効タイミング | 契約締結時(元気なうちから開始) | 判断能力低下後に家庭裁判所で後見監督人が選任されて開始 |
| 裁判所の関与 | なし(契約内で完結) | あり(後見監督人・報告) |
| 管理の柔軟性 | 高い(売却・賃貸・修繕等を契約で許容可) | 限定的(原則現状維持、許可が必要な場面も) |
| 対象 | 信託した財産に限定 | 基本的に本人の財産全体(身上監護も可) |
| 相続への備え | 承継先・使い方を事前に設計可 | 相続分配の設計は別途(遺言など) |
設定例(モデルケース)
〈夫婦×自宅〉モデル
- 委託者=夫、受託者=長女、第一受益者=夫、第二受益者=妻と設定。
- 夫の判断能力が低下しても、長女が自宅の売却やリフォーム費用の拠出を実行。妻の居住と生活費確保を継続。
〈親×収益不動産〉モデル
- 家賃収入の受取・修繕・更新を受託者(子)が実行。
- 親が施設入居になっても、収益を介護費や生活費へ充当。空き家化・資産凍結を防止。
司法書士法人entrustの支援ポイント
- 司法書士が設計~契約~登記までワンストップ。
- 不動産鑑定士と連携し、適正な評価・活用方針を提示。
- 資産税に強い税理士が贈与税・相続税の論点をチェック。
- 必要に応じて弁護士・土地家屋調査士とも連携。
- 芦屋・西宮・神戸・大阪エリアでの実務経験に基づく“現場解決力”。
よくあるご質問
-
家族信託だけで十分ですか?
-
医療・介護など身上監護は家族信託の対象外です。
任意後見や遺言と“組み合わせる”ことで、より安心な体制になります。
-
いつ始めるのがベスト?
-
ご本人が“元気なうち”だけが設計のチャンス。迷ったら早めのご相談をおすすめします。
まとめ
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、家族が主体的に動ける“やさしい仕組み”。
遺言や任意後見と上手に組み合わせて、今日から安心の土台づくりを始めましょう。
家族信託・遺言・任意後見のご相談は司法書士法人entrustへ。
初回ヒアリングで“わが家に合う設計”を一緒に整理します。
芦屋・西宮・神戸・大阪エリアに精通した実務経験でサポート。
お電話・メール・オンライン面談に対応(事前予約制)。
最新記事
CONTACT
お問い合わせ
司法書士法人entrustへのお問合せは、下記メールフォームへ必要事項をご記入の上、ご連絡ください。
お問合せ用メールフォームは24時間受け付けております。担当が内容を確認次第ご連絡差し上げます。
お電話でのお問合せもお受けしておりますので、お急ぎの方や直接話したい方はお気軽にお電話ください。
![]() 06-6147-8639
06-6147-8639